元マイクロソフト業務執行役員が語る〈世界水準のGo-To-Market戦略〉成長曲線を加速する実践的アプローチ

本イベントでは、株式会社エスプール執行役員 タクウィル事業責任者の境田がAI inside株式会社 執行役員 CPO、マイクロソフト株式会社 業務執行役員、シスコシステムズ合同会社 マーケティング本部長など、外資系大手でキャリアを積み、現在はIT/SaaS/AI領域でGTM戦略や組織構築を支援する北川裕康氏と共に、GTM(Go To Market)戦略 の立案方法・経営戦略・CRO視点の重要性についてお届けいたしました。
前回、北川氏にご登壇いただいた際は、「マーケ後進国から脱却「マーケ責任者の役割」の再定義成果を倍速化する世界水準のマネジメントとは」というテーマでお話いただきました。ぜひ、そちらの重要ポイントをまとめたイベントレポートも合わせてご覧いただけますと幸いです。https://takuwil.spool.co.jp/column/article/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e5%be%8c%e9%80%b2%e5%9b%bd%e3%81%8b%e3%82%89%e8%84%b1%e5%8d%b4%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2%e3%80%8d%e3%81%ae/
日本企業に足りない「世界基準」の視点
北川氏は冒頭、「日本のマーケティングは情報源が非常に限定的で、世界で当たり前に使われている枠組みの一部しか輸入できていない」と指摘しました。たとえば日本では「ザ・モデル」や「バリュープロポジションキャンバス(※)」が盛んに使われますが、実際の海外企業では必ずしも主流ではありません。
さらに、日本の多くの企業は「展示会」「リスティング広告」に偏り、特に中小企業向けに終始してしまう傾向があります。「これではエンタープライズ市場を攻略することは難しい」と警鐘を鳴らしました。
※バリュープロポジションキャンバス(VPC)…顧客のニーズと自社が提供する価値(バリュープロポジション)のずれを解消するためのフレームワーク
「いきなり結婚してください」と言っていないか
北川氏は「ジョブ理論」を紹介しながら、日本企業がやりがちな失敗をユーモラスに表現しました。
「顧客は製品そのものを買うのではなく、自分の生活やビジネスにおける“進歩”を買っている。ドリルを買う人が欲しいのは“穴”であり、ドリル自体ではない。にもかかわらず、多くの企業は“うちのドリルは刃先が硬い”と性能ばかり訴求してしまう。それは、初対面で“結婚してください”と迫るようなものだ」と語ります。
重要なのは、製品のスペック説明ではなく、顧客の「進歩・変革」をどう実現するかという視点です。顧客は進歩にこそ投資する──この考え方がGTM戦略の根幹にあります。
差別化の本質は「製品」だけではない
次に北川氏は「差別化」について語りました。
多くの日本企業は「自社製品の機能や性能」で差別化を語りがちですが、世界のトップ企業は 組織能力やビジネスモデルそのもので差別化を行います。
その典型例が Workday (※)です。人事領域で「HR Transformation」という概念を提示し、従来の縦割り型組織を、中央のチームのCenter of Excellence(COE)と各事業部をサポートするHRBP(ビジネスパートナー)、ファンクションベースの3つに再編。その進化を支える基盤としてWorkdayを導入させることで市場シェアを急拡大しました。単なるツールではなく「人事部門の進化」を売った結果、顧客は大きな投資を行ったのです。
※Workday…人事管理や財務管理などの企業オペレーションを統合する、AIを組み込んだクラウド型システム
GTM戦略とは「選択と集中」
北川氏は「GTM戦略は一言でいえば、優先順位とリソース配分を決めること」と説明します。
つまり「やることを決める」と同時に「やらないことを徹底して切る」ことが重要です。そのためには、外部環境分析(環境、市場、競合)、内部分析(製品・仕組みの差別化、パイプライン、リソース、ケーパビリティなど)を経て、狙うべきセグメントを明確化します。
ここで紹介されたのが セグメンテーションとフラグメンテーション です。
- セグメンテーション:企業規模・業種などで市場を区切り、勝てる領域にリソースを集中。局地戦では3倍の戦力で競合を圧倒する。
- フラグメンテーション:さらにアカウント単位に分解し、A、B、C、Dの優先順位をつける。
この2つのプロセスを経ることで、ようやく「勝てる戦い」に集中できるのです。
セグメンテーションとフラグメンテーションをしてアカウント(マーケティング対象となる特定の企業や組織そのもの)のどこを狙うかまで明確になるため、グローバルの会社ではABMを導入しているケースが多い傾向にあります。
マーケティングはWhyとHowだけでいい
北川氏が繰り返し強調したのが「日本の企業はWhat(製品機能)から話しすぎる」という点です。
マーケティングの役割は Why(なぜ存在するのか) と How(どう価値を提供するのか) をいかに伝えるかになります。
「What(何を提供するか)」は営業が適切なタイミングで語ればよく、最初から詳細な機能説明をしては顧客の共感を得られません。
パイプラインとデータドリブン経営
実務面では「パイプライン管理」が極めて重要です。パイプラインを積み上げて管理することで、売上予測(フォーキャスト)が明確になり、投資判断や営業リソースの配分が可能になります。
さらにCRMにおいて、ガバナンスを効かせて徹底して更新していくことが求められます。
北川氏は「ケーデンス(活動のリズム)」も成功要因として挙げました。定期的な会議やレビューのリズムを明確にし、全員が同じテンポで活動することで、改善のサイクルが回りやすくなるのです。
ABMを支える海外と日本の違い
GTM戦略を実行するうえで不可欠なのがABMです。ところが、日本企業は コンタクト情報の入手難易度 が高く、ターゲット企業へのアプローチが難しいという課題を抱えています。
海外ではZoomInfoやLinkedIn Sales Navigatorを活用すれば、ターゲット企業の意思決定者に直接アプローチ可能です。しかし日本ではその流通が限定的で、結局コールドコールに頼らざるを得ません。
北川氏は「顧問や専門家ネットワークを活用するのも一つの有効な手段」と提案しました。
まとめ:世界基準の視座で戦略を描く
北川氏の講演を通じて浮き彫りになったのは、日本企業がいかに 製品スペックや国内的なリード獲得手法に偏っているか という点です。
世界基準のGTM戦略では、
- 顧客の「進歩・変革」にフォーカスする
- 製品だけでなく組織能力やビジネスモデルで差別化する
- Why/Howを中心に語り、Whatは営業に任せる
- 勝てるセグメントを絞り、選択と集中で戦う
- パイプラインとデータドリブンで持続的成長を実現する
といった考え方が徹底されています。
グローバル基準の視点に学びながらも、日本独自の強みを活かしつつ、組織やプロセスを絶えず進化させることが、これからの企業にとって不可欠です。
この記事の監修者

-
清水 聖子
株式会社エスプール
ヒューマンキャピタル事業部 ニアバウンド支援部 サービス推進グループ

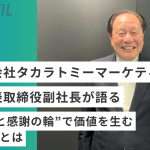

-150x150.png)
-1-150x150.png)